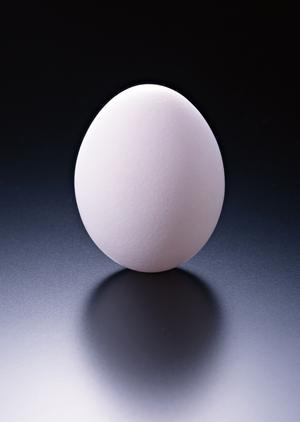湯浅醤油は醤油発祥の地で作られている
お醤油発祥の地がどこにあるのかご存知の方はあまり多くないと思われます。
発祥の地は和歌山県の湯浅にあります。
歴史は長く、いまから750年前にさかのぼります。
鎌倉時代の禅僧・覚心が栄(現中国)から伝えた味噌が醤油の母体となっています。
湯浅の地が選ばれたのは水が良かったからです。
江戸時代には1000戸の湯浅に醤油屋は92軒あったそうです。
しかし、時代と共に醤油屋は少なくなり、戦後20数軒残っていた醤油蔵は昭和45年には1軒だけになりました。
現在、江戸時代から続く醸造蔵で手作りを続けているのはこちらの「角長」だけです。
蔵は天保12年に建てられており、今もその蔵で醤油が作られています。
材料は国産丸大豆や国産の小麦、もちろん化学調味料や添加物などは使われていません。
水は湯浅山田の水です。
750年前、醤油作りに選ばれた綺麗なおいしい水が今も変わらず使われています。
昔と変わらず寒の時期に仕込みが行われ、約一年半丁寧に手作りで作られる湯浅醤油は現在、こちらの角長でしか手に入りません。
貴重なお醤油です。